これは
【付録】 続・日本人の「活気」と「ゆとり」はいつから消えたのだろう ~ ゲイテッド・コミュニティに向かう
の続きです。
ξ
劇作家・山崎正和氏(1934~2020)は、日本の1960年代に登場した新しい感性について次のように述べています。*1
たとえば50年代の青春文学を代表するのが石原慎太郎氏の『太陽の季節』だとすれば、60年代のそれとして、庄司薫氏の『赤頭巾ちゃん気をつけて』をあげることができます。
そこに出てくる青年像を較べてみれば、おのずと決定的な変化が浮かびあがってくるはずです。
石原氏の主人公が、勃起した性器を振りかざして外部の固い壁に突進する青年だとすれば、庄司氏の主人公は、つねに自分の内部にある「若さという狼」と闘い、「馬鹿ばかしさのまっただ中で犬死しないための方法」を考えている青年なのです。
「・・・つまりそういった種類の馬鹿ばかしいことがいっぱい書いてあるのだが、その中の最後の方に『逃げて逃げて逃げまくる方法』というのがあるのだ。
つまり、誰かがもしなんかの問題にぶつかったら、とにかくまずそれから逃げてみること、特にそれが重大な問題であると思われれば思われるほど秘術をつくして逃げまくってみること、そしてもし逃げ切れればそれは結局どうでもよかった問題なのであり、それは逃げまくる力と比例して増えてくるはずで、つまり、逆にどんな問題にとっつかまってジタバタするかでそいつの力はきまってくる、だから逃げて逃げて逃げまくれ、そうして、それでどうしても逃げ切れない問題があったらそれこそ諸兄の問題で。
そうだ、でもそうしたらどうするのだろう?」(庄司薫著『赤頭巾ちゃん気をつけて』、1969年刊)
なんだ、こんなことをしみじみわかるまでワタシはずいぶん時間がかかったのに、50年も前の小説の中であっさり言われていたんだ、と知って驚きます。*2
「どんな問題にとっつかまってジタバタするかでそいつの力はきまってくる」なんてところはカッコいいです。
「ノンポリ」の学生(高校生)として、ものごとに「やや距離をおいた眼差し」を維持して皮肉っぽくやり過ごしてきた主人公の文体には、自虐、自嘲、自己嫌悪ふうの諧謔が持つ饒舌さがあります。
しかし、主人公が「どうしても逃げ切れない問題」というとき、この当時、なにか理念的な生き方の選択、イデオロギー的な生き方の選択を言っているように聞こえます。
50年後のワタシが思い付く「どうしても逃げ切れない問題」は、こんな問題ではありません。
カネを稼ぐために仕事をすること、その知恵を絞ること、自分と家族の生活を守ること、それが「どうしても逃げ切れない問題」として最初に頭に浮かびます。
ワタシが変なのかどうかはちょっと棚上げして、50年後のこの感覚差はなんでしょう。
ξ
敗戦から20年経ったこの時期、日本資本主義は疾風怒濤のごとく発展していました。
この頃、人々は主として商業資本の伸展によって、次から次へと膨満化した情報に囲まれるようになりました。
これらは、当然、それまでのイデオロギー、法、教育、行政、宗教のような構造を持った情報から、無構造な情報に変化したものになります。
情報の伝え方に構造のあるものから、その伝え方が目に見える構造のないものへと変化が起こったのです。
例をあげれば、教育や行政や宗教は、構造的な情報の典型的なもので、誰が誰に情報を伝えるか、ということがはっきりしており、したがって情報伝達の当事者の姿もまた、人の目に見えます。
一方、60年代以降の都会を賑わせた、いろいろな情報は、ファッションにしても事件のニュースにしても、またスターの魅力にしてもベストセラーにしても、誰が作り出して誰に伝えるものであるか、あいまいになり極めて特定しづらくなりました。
むしろ特定などする必要すらなくなった無構造な情報が奔流するようになっていきました。
それ(無構造な情報)は、社会自体が生み出して、社会全体が受け取り、社会全体が増幅していく不思議な構造を持っています。
都市はたんなる工業生産の場所でもなく、また人口吸収の場所でもありません。
それは、なにより広い意味での、文化と無構造な情報を生み出す場所であり、そういう場所として、ほとんど数千年にわたって存在しつづけたものなのです。(前掲書)
この小説の学生主人公は、社会が構造を持った情報に支配される時代から無構造な情報に劇的にシフトしていく時代に自分が居ることを察知していたと思います。
彼らは当初、自嘲、自虐、皮肉、諧謔を伴なう「やや距離をおいた眼差し」からは始めるしかなかったかもしれませんが
「我々ワァ!」「断固としテェ!」「立ち上がることをォ!」「訴えたいと思いますッ!」という旧世代の、構造を頼った情報しか発信できない救いがたい連中より
急速に膨満化しては情報の無構造化に突っ込んでいった日本資本主義の、ユートピアのようなディストピアのような、その行方にはるかに鋭敏だったように見えます。
ξ
1970年代に飽和しかかった日本資本主義は、無構造な情報を雨あられのように降り注ぎ溢れさせていました。
つまり収入も貯蓄も確実に伸びてはいるのですが、法や教育や行政や宗教やらの構造を持った情報の存在感がおそろしく希薄になる一方、マスメディア、口コミを通じた責任、秩序、方向、軽重、距離感などまるで不確かな情報が、<無限大>に拡大していくようなフィクションの中で生きることになりました。*3
言い換えると、産業の要求するような無限の消費などそもそもできないのですが、感性(脳)はまるで<無限大>の選択肢を与えられたような、フワフワとした心地よいフィクションを存分に可能にしました。
これは脳が身体から離れ、いくらでも拡張していこうとする経験といえます。
ξ
一方、この無構造の世界は、無構造だからこそ誰にも大きな道筋をつけてもらえない、しかし誰かを頼りにするほかない、人の顔色をうかがってみるしかない、でも自分でしか決められない、どうすればいいという、不安、疲労を同時にもたらしました。
それは現在でも、処方箋のない、絶え間ない不安や疲労として続いています。
しかし庄司薫の描いた学生主人公たちのその後
さらに自由に無構造な情報が溢れた1970年代
日本資本主義が初々しい飽和期に入った頃
不安も疲労も、その結果生じる悪意もまだ薄く覆われ
そのフワフワした心地よさを味わうことのできた幸福な時代がありました。
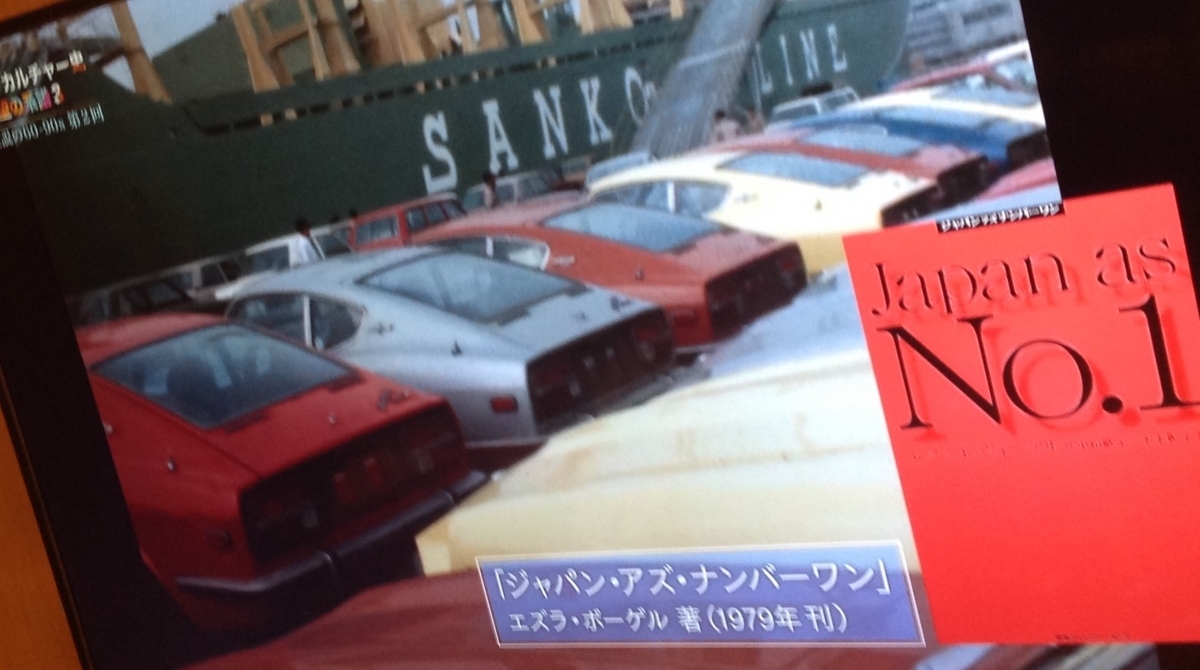
ξ
現在を知るために、戦後の20世紀を知りたいのだと格好つけたところで、ワタシは文字か映像の情報に頼るしかありません。しかし心して浸ってみることは必要です。
1970年代に登場した尾崎亜美という天才シンガーソングライターの、時代のフワフワとした心地よさを捕らえた「マイ・ピュア・レディ」の流れる、資生堂クリスタルデュウのテレビCM(1977)を見つけました。
モデルの少女、小林麻美の語りは次のようです。
目の前のものでいいんじゃない? 今ここにあるもの
本当に今、自分がこう感じたからね、すごくハッピーになれて
泣きたいときに、すごく素直に泣けて
そういうふうに自分の気持ちに素直に生きられるってことが、ピュアってことじゃないかなって思うのね
ハッピーと思えばいくらでもハッピーになれたかも知れなかった無構造な情報時代のフワフワとした心地よさの頃
「私らしく一日を終えたい *4」「自分の気持ちに素直に生きたい」、そんなファンタジーが(日本に)ようやく可能になった頃
こういう化粧品CMができていたんだね、とそれこそフワフワとした心地よさを味わいました。